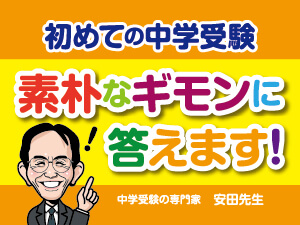都内最大の出願者数の適性検査型入試から得意を生かせるAAA(世界標準)入試など12種類の入試をラインナップ。日本一入試方法が多い学校法人宝仙学園順天堂大学系属理数インター(以下、宝仙学園)は、受験勉強が間に合わなかったお子さんにも門戸を開き、“自分にあった入試を見つけられる”人気校です。もちろんその人気は、入学してからの学びや学校生活に根ざしたものであり、それが入試にも現れているからに他なりません。本取材では、12種類ある入試の中のプレゼン型とアクティブラーニング型の入試について、入試広報部長 米澤 貴史先生にお聞きしました。

プレゼン型やアクティブラーニング型入試を導入された理由をお聞かせください
「私立の入試というと、塾に通って2科4科や公立一貫型のペーパーテスト対策のために勉強して、となりますが、塾に通っていなくても、また受験勉強が間にあっていなくても、目に見えない能力や個性を持った子はたくさんいます。そんな子たちに門戸を広げていこう、見える学力ではなく見えない学力を見ていこうということからはじめた入試です」

12種類の中で新タイプ入試にあたる入試は?
「12年間の学習歴や自身の成長をアピールしてもらう『リベラルアーツ入試』、アスリート、アーティスト、アカデミックの各分野で全国レベルの実績を持ち世界に飛び出そうとする人を対象とした『AAA入試』、英語でプレゼンテーション面接を行う『グローバル入試』、自分の好きな本をプレゼンテーションする『読書プレゼンテーション入試』、テーマに基づいて自分の意見を発表する『オピニオン入試』と、グループワークを行う『入試理数インター』が、新タイプの入試です。ここでは説明しきれないので、ぜひ説明会(要予約)や入試体験会(要予約)にお越しください」
説明会も入試体験会も予約制。人気校ゆえにすぐに埋まってしまうそうですが、追加開催もあるので、学校のホームページはこまめに要チェックです。
プレゼンテーション面接は、どんな点が評価されるのですか?
「小学校時代に熱心に取り組んできた活動を学習歴として学習歴報告書(事前に提出)に書いてもらい、それをもとに試験当日の面接で自分をプレゼンテーションしてもらいます。基本的にフリースタイルなので、映像で紹介してもらってもパネルを使ってもいいのですが、一番見ているのは、本人の体験からどういう成長があったのかを自分の言葉として語れているかどうかです。グループワークでは最初はいいことを言おうとしていても、90分の中でだんだん素の姿になっていきます。私たちが知りたいのはどんな資質を持った子なのかです。ぜひありのままの自分の言葉で話してください。またプレゼンテーション型入試には教科の試験はありませんが、日本語リスニングの試験があります」
日本語リスニングはどんな試験なのでしょうか?
「音声で聴いた話の主旨を正しく理解できたか、また理解したことを応用して課題解決するテストです。これは入学後、授業を理解しコミュニケーションがはかれるかを見るために行なっています。問題は、言っていた内容を聞く問題より、内容に対してどう考えるかを聞く問題の方が多く出題されます。日本語リスニングは、体験していただくのがわかりやすく、サンプル問題を用意していますので、ぜひチャレンジしてみてください」
日本語リスニング・サンプル音源
https://www.hosen.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2017/01/fcaee2909c2d0fe6ef70a57757d3d638.mp3
日本語リスニング・サンプル問題
https://www.hosen.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2017/01/06cfbc44dc9c723e3b49440cb925236a.pdf
新タイプ入試は、どんな学びにつながっていくのでしょうか?
「新タイプ入試の中でもグループワークを行う『入試理数インター』は、本校らしい入学後の学びに直結した入試です。学校のニックネームにもなっている理数インターの名前を飾った、教科『理数インター』の授業は、理数的な思考(繰り返し挑み論理的に考える力)を楽しく鍛えながら、コミュニケーション能力(心と心を通わせる力)やプレゼンテーション能力(発送や思考などを発表する力)を協働の中で身につけていく授業です。教科『理数インター』のテーマは『答えのない学びをしよう』。これからの時代を生きていくための、自ら求め、切り開いていく能力の育成にあります」

「はじめからトップギアに入れない」「12歳は、偏差値より学習歴!」と謳う同校では、丁寧にレベルアップをサポート。中学1年で身につけるのはコラボレーション(グループで協力し合い仲間とコラボレートしながら問題を解決)ですが、まず居場所と居心地をつくることを大切にしており、米澤先生が先日中1の教科『理数インター』の授業で行ったのは『ドミノ倒し』。一見遊んでいるように見えますが、対話のきっかけを創っているそうです。その他にも演劇ワークを行ったり、理数インターというと理科や数学のイメージを持ちますが、全くそうではありません。米澤先生が校長室に呼ばれ、教科『理数インター』の授業をつくる際に注文されたのは「この授業が楽しくて学校に行きたくなるような授業をつくってほしい」だけだったといいます。

教育は指導ではなく支援という考えの名物校長。「プレイヤーは生徒。教員はコーチ。保護者はサポーター。卒業生は後輩のために一肌脱いでくれる兄貴と姉貴。学校はその構成員たちが、それぞれの持ち場で貢献し合うプレイヤーズ・ファーストの『知的で開放的な広場』」という考え方など。宝仙学園は、多彩な魅力で多くの受験生を集め、210名前後が入学手続きをする超人気校。入口はたくさん用意されているので、きっとあなたにぴったりの入試を見つけられるはずです。
教えて!学校のこと 試験のこと
中学2年生にお話を聞きました。
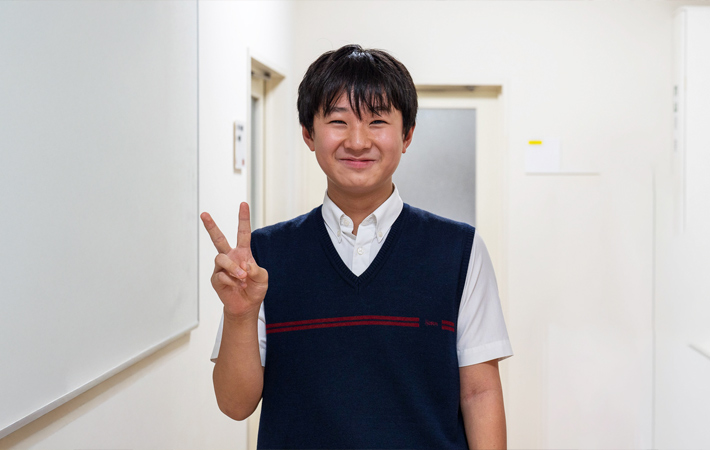
宝仙学園をどこで知り、受験校に選んだ理由は?
「兄と姉が宝仙に通っていて、何度も来たことがあって、楽しそうな学校だなと思っていました」
受験した試験を選んだ理由は?
「リベラルアーツ入試を選んだのは、読書は向いてないし英語も苦手なので消去法で選んだ感じ?でも人前で喋るのも苦手です。4科も受験しました。あと校長先生が大好きです」
なんとR.Oくん、校長先生が大好きでiPadのカバーにサインをしてもらい、それを毎日使っていると言います。

部活は水泳部とボランティア部。
日本語リスニングの試験はどんな試験か知っていましたか?
「ホームページにあった音声を聞いて練習をしました。英語リスニングが日本語になったようなものだと思いました」
試験を受けてみた感想は?
「小学生1年4年?の時からずっとやっている農業?というか、植物に対する病気の対策についてプレゼンテーションしました。試験のためにお父さんのパソコンで資料はつくりましたが原稿はつくりませんでした。たくさん喋って質疑応答の時間が少なかったのですが、緊張していて何を質問されたか覚えていません。姉もリベルアーツ入試だったのですが何を話したか覚えてないといっていました。好きなことの熱が伝わればいい試験なのではないでしょうか」
試験のために何か準備をしましたか?
「原稿は作らなかったのですがネットで集めた画像を資料としてまとめました」
実際に入学して感じたことは?
「体育祭とか宝仙祭(文化祭)とか、思ってた以上に生徒が中心だな、と思いました。学年だけでなく先輩とも仲がいいです」
将来やりたいことは何ですか?
「プログラミングを勉強して、農業の虫や病気を発見するAIを作ってみたいです」
これから宝仙を受験する人へのメッセージをお願いします。
「リベラルアーツ入試を受けるなら親からいわれたものではなく、熱意があって心の底から自分が好きなものを発表して欲しいです。学校にはポジティブな人が多いし、ネガティブな人もポジティブな人の影響を受けて明るい雰囲気の学校です。先生と生徒の距離感も近い学校なのでおすすめです」
- 取材Memo
-
名物校長の富士語録
iPadに「自己ベストの更新」と富士山のサイン。生徒にサインをお願いされたのはじめてだったようで、富士校長もその時はちょっと驚いていたとR.Oくん。「挑戦なくして成長なし」「なぐさめ はげまし きたえる」「答えのない学び」「明るく楽しく一生懸命」「温かみのある学校」など、富士校長が放つ数々のメッセージは、それが意味することを知れば知るほど心に響くメッセージ、ファンがいるのは大納得です。またメッセージは、生徒のみならず、教員にもよく話しているそうで、それは「学校が持つ固有の文化を知ってもらい、その文化に価値を感じる人と対話する」ためだそう。もっと知りたいと思った方は、ぜひ説明会へ。(富士校長ファンになっても取材者は責任をとりませんが)