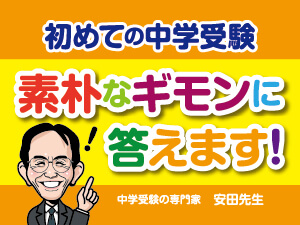自修館中等教育学校は、1999年の創立時から「探究」を授業に取り入れています。今や探究は、どの学校でも行われていますが、自修館の場合は「探究」を教育の3本柱のひとつと捉え、ミックス型教育によって「自学・自修・実践」できる生徒を育成しています。自修館の教育と、同校が導入している探究型入試について、小河校長、森教諭、除村教頭にお話を伺いました。

なぜ3つの柱による教育を行っているのでしょう。
本校の学びの柱は、「探究・グローバルマインド・EQ教育」の3つです。ひとつめの柱となる「探究」では学び方を身に付け、自分で物事を進め、問題解決ができる力を養います。本校の探究は、調べ、まとめ、発表して終わるのではなく、グループで行うにせよ、ひとりで行うにせよ、外側からの評価も伴うことが特徴。それを実践するには自分とは異なる価値観や文化を理解し、受け入れる力である二つめの柱「グローバルマインド」が必要になるわけです。さらには高いコミュニケーション力も重要で、これを養うのが3つ目の「EQ教育」です。EQとは、「Emotional Intelligence Quotient」で、こころの知能指数という意味です。
探究に限らず、すべての学校生活において、「探究・グローバルマインド・EQ教育」の3本柱を融合させることによって「自学・自修・実践」できる生徒を育成することが本校の教育方針です。
3本柱のひとつである探究教育は、26年前から実施されており、しかも在学中の6年間継続して行われています。工夫されている点などはありますか。
探究も学習も、全員が簡単にこなせるものではない、という考えを前提として取り組んでいます。というのも、小学校を卒業したばかりの生徒に「探究をやりましょう」「教科をしっかり学びましょう」と言ったところで、本当に自発的にできる生徒は3割程度です。そのため本校では、探究も学習も、形、つまりやり方をしっかり教えることからスタートします。
探究は時間割の中に週に2回組み込んでいますから、他の科目と同様の感覚で進めることができます。1、2年次はクラスをいくつかのグループに分けて、グループごとにひとつのテーマを探究します。調べ方はもちろん、外部の方に聞く場合はどうやってアポイントを取るのか、発表はどうやればよいのか、といったすべての形を基礎から指導しながら進めます。そして各自が「形」を理解し、できるようになった3年次以降は、ゼミ形式で自分の興味に沿った探究に取り組みます。
ただ「やりなさい」ではなく、しっかりと形を整えたうえで自分のオリジナルを出していくことが、本校の探究のスタイルです。
最初にグループで探究を行うメリットは何でしょう。
グループ内には、積極的な子、消極的な子、教えるのがうまい子、調べることが得意な子、発表が得意な子、など、いろいろなタイプの生徒がいます。グループで行うことで、積極的な子が消極的な子を引っ張り上げたり、最初はあまりやる気がなかった子が、友人の姿から刺激を受けたりします。学び合いや助け合いなど、教員が想像していた以上の変化や成長を目の当たりにすることも多々あります。
本校は探究に限らず、探究以外の授業も習熟度別にはしていません。それは一見効果的には見えないかもしれませんが、互いの学び合いによって、学びを深めたり、広げたりするにはとても効果的ではないかと考えています。
3年次からの探究は、ゼミ形式で行うのですね。
1~2年で探究の土台をつくったうえで、3年、4年(高1)の2年間はゼミに所属して、個人が定めたテーマに沿って探究をすすめていきます。自由度が高いことが特徴のひとつですが、定期的に面談も行い、進捗状況を確認しています。テーマが自由なので、教員も驚くようなユニークな探究や、専門的な分野に挑戦する生徒も多いですね。
本校の「探究」の捉え方は、「探し究める」なんです。調べて発表したら終わりではなく、その先もずっと続く「探究」を各自が見つけることがねらいです。自走につなげ、つねに前に進んでいく力を養うことが大きな特徴だと思います。
外部との接点も多いそうですね。
1年次から本校がある伊勢原市の行政や、近隣の大学・研究機関と連携し、探究を軸に意見交換や発表の機会を設けています。3年次以降はさらに外部の施設や企業への取材や協働の機会が広がります。外部の方々からフィードバックを受けたり、お褒めの言葉をいただくことは、生徒にとっての自信につながります。「頑張っているね」という言葉も、いつも接している親や教員からかけられても、生徒にはあまり響かないでしょう(苦笑)。でも外部の方から言われると、すごく響くし心に残り、その先の意欲にもつながります。
生徒さんの成長ぶりを目の当たりにしたエピソードはありますか。
たくさんありますが、このエピソードをぜひお伝えしたいと思います。近隣の小学校に行って一緒に探究活動を行ったグループがあるのですが、メンバーの中のひとりの生徒が、「将来は小学校の先生になりたい」と将来の夢を語ってくれたのです。その生徒は、中学時代はさほど積極的ではなかったというか、目標が見いだせなかったタイプの子だったのですが、小学生との探究活動を通して、彼のなかで何かが見えてきたのだと思います。その発言を境に、とても前向きになりましたし、勉強にも熱心に取り組むようになりました。活動を通して、自分の将来を思い描けるような生徒が出てきたことは、とても嬉しく思いますね。
また、仮説を立て、順序立ててものごとを考え、結果にたどり着く、といった探究のサイクルは、勉強や部活、委員会活動、行事運営などにも役立っていることが時おり見受けられます。こうしたサイクルは、社会に出ても一生使えるサイクルだと思うのです。
探究入試について教えて!

自修館への入り口のひとつとなる探究入試について教えてください。
本校の探究に興味を持って入学してくる生徒が昔から一定数おりました。たまたま学校見学に来た小学生が、探究の授業を見たら楽しくて、「自分もやってみたいけれど、今から受験勉強が間に合うだろうか」という質問も時々いただいていて。だったら探究目的で入学したい層の応援ができれば、という想いで探究入試を導入しました。
どのような問題形式なのでしょう。
県立中等教育学校の適性検査を意識した内容です。探究入試で受験する層は、平塚中等教育学校や相模原中等教育学校を第一志望あるいは併願校とする生徒が多いですね。
身近な題材を取り入れて、それを読み取りながら設問に答えていく形式で、記述も多いです。資料をいくつか出しているので、知識としてはさほど必要ないのですが、資料を正しく読み取る読解力や、そこをどう自分の考えにつなげていくかといった想像力や思考力、記述に欠かせない表現力を総合的に見ています。
探究入試に合格するためには、何をどう学んでおけばよいでしょう。
学ぶというよりも、いろいろな経験をして、さまざまなことに疑問を持てる視点を持ってほしいと思います。本校の問題は、探究型入試だけでなく、教科型の2科4科入試でも、いろいろな経験をして、自分で考え、表現できるタイプの子に合う設問が多いのです。
たとえば植物なども、ただ図鑑を眺めるのではなく、実際に見て触れておくとよいと思います。身近なことに「なぜ」という疑問を感じて知りたいと思う思考や行動力があると、入学後の探究もとても楽しくなると思います。文章を読む習慣もプラスになるでしょう。
またご家庭でもいろいろな話題に興味を持って話をする機会をたくさん設けてもらうといいですね。中学受験ってとにかく大変というイメージがありますが、本校の探究入試は、「辛い」「大変」ではなく楽しんでいろいろなことに興味を持つことがスタートなのです。
正しい答えを出さなくてもいいんです。小学生なりの視点で疑問を感じて調べて答えを出す。失敗して結果が出なくてもかまいません。大学や大学院、企業がやっている研究だって、ずっと失敗の繰り返しですよね。「調べたい」「知りたい」という意欲を大切に考えていますし、そうした意欲を持つ生徒にとっては、とてもおもしろい学校生活が待っています。
探究入試と、教科型入試で入学した生徒は、入学後、別クラスで学びますか。
いえ、同じです。最初はやはり教科型(2科4科)で入ってきた子のほうが知識量は多いのですが、探究入試で入学した子がハンデを感じないような授業を各科目の教員が工夫をこらして行っています。勉強のやり方をきちんと教えればできるようになりますし、探究入試で入学した子は発信力や人の意見を聞く力などに長けているので、すごく伸びます。
最後に受験生と親御さんにメッセージをお願いします。
まず学校見学に来ていただいて、本校のありのままを見てください。探究の授業も通常の授業も自由にご覧いただけます。また探究に役立つ資料が豊富に揃う図書館も一見の価値ありです。学校説明会では、具体的な事例も含めて本校の探究入試についても説明していますので、ぜひご参加ください。
探究入試の受験者は年々増していますので、今後は探究入試による入学者も増えていくと思います。
また、私たち教員も探究入試の問題を楽しみながら作っていることをお伝えしたいですね。ニュースや話題はつねにチェックして、教員同士でワイワイと意見交換しながら問題作りをしています。
教えて!学校のこと
S.Aさん(高校1年生)

Q1 なぜ自修館を探究入試で受験しようと思ったのでしょう。
第一志望校が相模原中等教育学校で、適性検査受験に向けて勉強していました。塾の先生から「自修館の探究入試も似た問題形式だから、過去問をやってみたら」と勧められ、やってみました。それがきっかけで併願校として考えるようになり、どちらも受験。結果、第一志望には落ちてしまって自修館に入ったのですが、今は自修館に入学してよかったと思っています。自分にとても合っている環境で、すごく楽しい学校生活です。
Q2 入学後の探究活動について教えてください。
中1のときは、伊勢原市の環境についてグループで探究し、2年のときは新型コロナウイルスのワクチンについて探究しました。1年のときはグループ内で私は受け身な感じでやっていたのですが、1年間やると、探究の流れや役割分担の大切さもわかってきたので、2年目になると、自ら動いてできるようになりました。また1年次は発表の際も、質問されると答えられないことが多かったのですが、その反省を踏まえ、2年次には仮説を立てたり、質問されそうな内容を事前に皆で調べて発表に臨みました。
Q3 今はどのような探究を行っていますか。
日本と韓国のK-popアイドルの違いについての探究を行っています。衣装の違いや、ミュージックビデオの違いなどを調べてまとめ、発表に向けて準備しています。私はもともとどちらのアイドルも好きなのですが、一見似ている両国のアイドルも、よくよく観察すると、異なる部分があるんですね。だったらそこを調べてみようと思いました。たとえば衣装は、K-popアイドルの場合は市販の服をアレンジして着用していることが多いのですが、日本の場合は、一からデザインしたものを着ています。自分の好きな分野なので、調べることが苦にならないし、とても楽しいです。
Q4 自修館のここが好き!を教えてください。
校外で参加できるイベントや活動についてもまめに告知してくれるので、興味があることには積極的にチャレンジできます。私は学校で紹介されたグローバルユース国連大使という活動に参加しています。各地区からの代表に選ばれ、さまざまな活動をしている方の講義を受けたり、貧困問題を学ぶためにカンボジアにも行きました。実際に現地に出向いて学ぶことで、問題をよりリアルに体感できましたし、日本との価値観の違いもわかりました。やりたい!と手を上げれば応援もサポートもしてくれるので、とてもありがたいです。
Q5 そうした活動を通じて、将来の目標なども見えてきましたか。
まだ目標や夢は決まっていませんが、環境問題には小学校時代から興味があり、さらにグローバルユース国連大使活動などを通していろいろな経験をしているので、環境問題解決への支援に関わることができたらいいな、という想いはあります。
- 取材Memo
-
印象的だったのは、お話を伺った先生方、生徒さんの口調や表情がとても穏やかだったこと。それに加え、イキイキさも感じました。だから、とても居心地がいいんです。また、探究ゼミでは本格的な課題に取り組む生徒も増え、サポートする先生方の知識も追いつかなくなることがあるそうです。それを逆に先生方も楽しみながら、自ら調べ、生徒と並走する。自修館の探究は、先生も一緒に「楽しめる」ことがポイント。取材時に感じた印象の背景には、学校全体が共有する「楽しさ」があるからなのだと思いました。