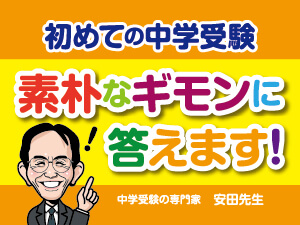2026年に創立100周年を迎える八王子実践中学校は、八王子で最も古い歴史を持つ私立中学校・高等学校。バレーの強豪校として有名な高校は1学年15クラスの編成ですが、中学校は1学年1クラスという少人数のクラス編成。生徒と先生が密に相談できる時間が多く、学習以外の相談にも答えてくれる、一人ひとりの学びと成長を手厚く見守る教育を行っています。
同校への入口となる入試は、2019年に2科・4科入試を廃止し、「中学受験をするのに、習い事をやめ、塾に行き、2科4科の勉強をして合格というのではなく、子供の可能性を見るのに、他の見方があるのではないか」と、入試をすべて新タイプ入試にするという入試改革を実施。その結果、様々な個性をもつ生徒が集まり、学校が「個性と才能を自由に伸ばす 一人ひとりが輝ける場所=Diversity」になっているといいます。
適性検査の対策はどのようにすればよいでしょうか。
「適性検査の問題を難しいと思われる方も多いと思いますが、適性検査に限らず難関国公立校の問題は、すべて基礎的なことの積み上げです。その結果として難しく見えるだけで、積み上がった問題をたどって解いていく力があれば解けるのです。ただ解く際に引き出しが一つしかないとそこからしか進めないので、引き出しは3つ4つないと解くスピードが上がりません。ではその引き出しは何かというと2科4科の力です。適性検査は2科4科の力がない子はできません。裏を返せば2科4科の力がある子は適性検査ができるのです。中学受験をするご家庭は4年生くらいから考えると思いますが、2科4科をやりながら5年生くらいから適性検査の問題に触れて、6年生でどちらで受けるか決めるといいと思います。2科4科の力がないと入学してから苦労することもありますので、2科4科はしっかりやることが大切です」
問題を解くスピードを上げるためのポイントは?
「問題に触れる量が大切です。というのはいろいろな入力に対して早く反応するためにはある程度の数をやっていないとできないからです。問題を解くのは最初はじっくりでかまいませんが、だんだん早くして6年生の10月から12月頃に一番早い状態に持っていき1月は総復習にあてると良いでしょう。ただ中には突飛な問題に出会うことがありますが、それは飛ばしてかまいません。解く問題は、回答への道筋が偏っていたり1つしかないものではなく、3、4つの道筋から回答にたどりつけるものが良問ですのでそういう問題を解いてください」
どんな問題を良問として見極めればいいのでしょうか?
「問題の題材が、身の回りのことから入っていって、それが問いに素直につながる問題がいい良問だと思います。本校の過去問に、円形と三角形のロボット掃除機を比べて、掃除できない範囲を考える問題があるのですが、これはまさに身近なことから入って小学校で習った知識をもとに掃除できない範囲の出し方の考えを回答する問題になっており、公立一貫校の問題と同様な問題になっています。この度、過去問集を作りましたので、ぜひそちらで確認してください」
過去問集は全64ページ、過去問だけでなく、模範回答や出題の基本方針、八王子実践が考える教育についても触れられおり、ぜひ説明会に参加して入手したい、非常に充実した内容の冊子です。
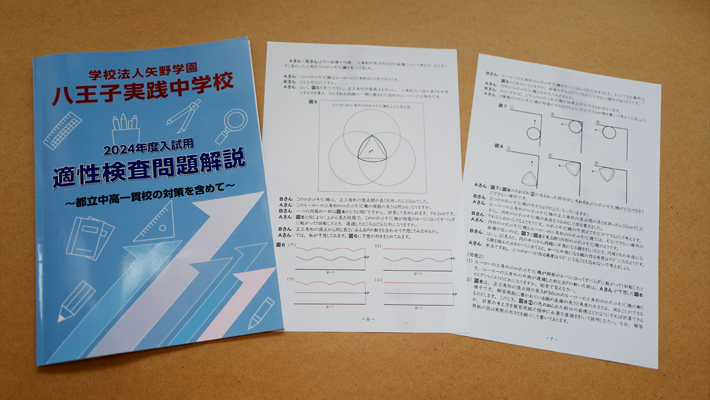
適性検査の作問をすると授業のレベルも上がる?
「適性検査の作問には12名の教員が携わっていますが、適性検査の作問で大切なのは、『何がいいたいか』をパッと掴めて『その表現は合っているか』です。これは受験生にも求められることですが、作問側もこれが読めない教員は、核心が掴めず問題を作れません。また核心にたどり着いても、『この設問でどんな答えが出されるのか』『その答えはこちらが求める答えにたどり着くのか』等々、教員同士がやり合って深めていくのですから、その深めていく過程が教員の知恵肉となり、それが授業にも反映されていくのです。2科4科を教える教員ではなく、適性検査の作問ができる教員であることはとても大切なことなのです。実は教えることと学ぶことは同じで、それは止まることなく進化と深化を続けていくものなのです」
先生が成長すると生徒も成長する。生徒が成長すると先生も成長する。この良循環こそが、学校を次の高みに押し上げていくポイントなのではないでしょうか。

適性検査に向いている子はどんな子なのでしょうか
「知的好奇心がある子です。4年生でも時間をかければ適性検査の問題は解けますから、2科4科の勉強の合間に、適性検査の問題を入れてみると良いでしょう。2科4科の勉強ばかりですと飽きてしまいますから、適性検査の問題を差し込んでみるといいと思います。その際に、適性検査の問題ときちんと正対でき、自分の勝手な思い込みでなく『この人は何をいっているのかな』と考えられ、答えるための要素がきちんと整理でき、なおかつそれを正しく表現できる子が適性検査に向いていると思います」
適性検査では、情報を正しく早く読み取り、それを整理した上で、表現できることが求められますが、なかなかそんな力を育ててくれる塾はありません。作文のテクニックは教えてくれても、正解のない表現を教えるのは至難の業。大切なのは「問題をよく読みなさい」ではなく、「相手をわかってどういう意図で聞いているのかを理解して答えなさい」。これを小学生が身につけるためには何をすればいいのだろうか。
適性検査に備える方法はあるでしょうか
「生まれた月でも違いますし、兄弟の有無でも子供の発達段階は違います。保護者は子供の発達段階をわかった上で、一人の人間として接し続けることが大切です。例えば家の片付けにしても、子供と一緒にやって、前に片付けたのにどうして散らかってしまったのか。それは大きさで片付けたからだったのか。場所だったか。それでは今度は種類で片付けてみようなど、整理の仕方を考えるようにすると分析して考えるクセが身につきます。手間暇はかかりますが、『片付けなさい』ではダメなんです。また小学校でも、あらゆる活動を人任せにしないで、積極的に参加して『こういう風にABCで分けてみよう』とか、ファクターを決めてそれを評価する訓練ができるといいですね」
適性検査には、作文力が必要、図表を読み解く力が必要、読み込める力が必要などといわれますが、本当に大切なのは、何よりも本質を探究する姿勢、つまり知的好奇心があるかどうかなのだと思いました。

https://www.youtube.com/watch?v=VIdzE2IgTAs
来年受験を考えている受験生や保護者へのメッセージをお願いします。
「2022年入試から南多摩中等教育学校の併願受験を狙う受験生のための試験問題として出題しています。南多摩中等教育学校の併願を考えている受験生は、年数回行っている問題解説に参加すると受験対策になります。また本校の適性検査型入試で入学した生徒は、本校難関のJ特進への進学、そして難関国公立大学進学を目指します。南多摩中等教育学校の併願校をお探しの受験生は、ぜひ本校の説明会に足を運んでみてください」
事実、八王子実践の適性検査受験者の上位5名の内、3名が南多摩中等教育学校に合格したことを耳にしたといいます。また今後は中高一貫校としてのさらなる教育改革も予定しているという同校。公立校受験の併願校として見逃せないだけでなく、今後は人気校として狭き門となってしまうことを予感した取材となりました。
- 取材Memo
-
ノートを手書きでとるということ。
ICTを使った授業が人気ですが、学校としては、ICTの良さは認めつつ、あえてタブレットではなく、手書きでノートを取らせる授業を行っているといいます。なぜなら「知識は思考を早くする」ので、やはり知識は必要。自分で手書きでノートをとって、自分が理解したことを自分で書いて自分の知識にすることがとても大切だといいます。実際にタブレット学習と手書き学習の比較実験では手書き学習の方が定着率が高いという結果が出ているとのこと。AI時代には検索でなんでもわかるので知識は不要という意見もありますが、「検索できない時はどうする?」、また「知識があれば検索している時間に考えられる」ので、やはり知識を持っていることは強さことであり、手書きは普遍の学び方といえるのではないでしょうか。