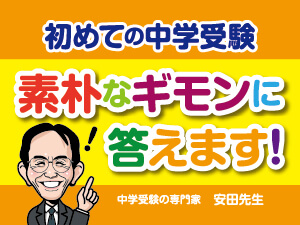多摩エリアにある学校は、「駅からバス通学」とのイメージがありますが、「八王子学園八王子中学校」は、JR中央線西八王子駅から徒歩わずか5分。通いやすさと面倒見のよさ、スポーツも強い文武両道の学校として注目されています。また、2016年からは適性検査型入試を導入。受験者数、入学者数も年々増加しています。
今回は、「八王子学園八王子中学校」の適性検査型入試と学校の魅力について、募集広報部の波平先生にお話を伺いました。

「適性検査型入試」を導入した背景を教えてください。
多摩エリアは都立中高一貫校の人気が高く、なかでも同じ八王子市内にある「東京都立南多摩中等教育学校」を目指す小学生が多々見受けられました。それならば本校も「適性検査型入試」を実施すれば、問題も似ていることから、受験生にとってより併願しやすくなるのでは、と考えました。
こうして2016年度入試から「適性検査型入試」を導入しましたが、この入試を利用する受験生は年々増えています。従来型の2科4科型も行っていますが、適性検査型入試で入学する生徒との割合は5:5と、約半数を占めています。
「適性検査型入試」で入学した生徒の特長を教えてください。
入学後は、入試のタイプ別にクラス分けをすることなく、どちらの入試で入学した生徒もクラスで学びます。適性検査型入試で入学した生徒は、国語力が高い傾向があります。また、その後の伸び方を模試の結果などから追跡してみると、同じ偏差値帯の学校よりも国語力が高いことがうかがえます。
「適性検査型入試」の傾向と対策について教えてください。
まず内容に関しては、南多摩中等教育学校の入試を想定した設問となっています。本校で行っている「適性検査型入試」は、Ⅰ(配点100点、試験時間50分)が文章を読んだ後、質問に対し600字程度の文章を書く問題で、Ⅱ(配点200点、試験時間50分)が算数・理科・社会の融合問題です。受験生は、Ⅰ、Ⅱどちらも受験します。Ⅱに関しては、数的な処理能力も必要となる設問になっていることが特徴です。これからの時代はデータサイエンス系の処理能力がますます必要になりますので、そうした傾向も見据えて設問を作っています。
対策に関しては、とにかく過去問を何度も何度も解いて、慣れていくことが一番だと思います。また、Ⅰは読む文字量も多いので、日ごろから読書などで活字を読む習慣をつけておくとよいでしょう。Ⅱも文章量と情報量が多いので、試験中に時間が足りなくなったら、次の設問に進む勇気も必要です。入試は満点を取らなければ合格できないというわけではないので、とっさの状況判断ができる強さを身に付けておいてほしいですね。もっとも何度も過去問にチャレンジしていれば、時間配分もわかってくると思いますので、都立中高一貫校の問題も含め、適性検査型入試の過去問は慣れるまで何度も解くことをおすすめしています。
「八王子学園八王子中学校」の魅力は何でしょう。
面倒見の良さと文武両道ですね。近年は難関校への合格実績も伸びています。その背景には、基礎力の養成と徹底したフォローがあります。本校は、成績上位者を伸ばすと同時に、成績があまり芳しくない生徒へのサポートにも力を入れており、全体的な底上げを目標としています。
具体的には、とにかく学校内で徹底的に手厚いサポートを行います。もちろん自宅学習用の課題も出しますが、学校内でできるだけ学びを完結できる体制づくりを整えています。
本校は先生の数が多いので、生徒が質問にくれば必ず対応できます。たとえば自分が習っている教科の先生の手が空いていなければ、同じ教科の先生が、学年、クラスを超えて対応します。質問難民になるようなことは、本校では起こりえないので、生徒も気軽に職員室にやってきます。職員室前では毎日多くの生徒がマンツーマンの指導を受けていますよ。

進路選択も、生徒一人ひとりの目標や意思を尊重します。本校は、「東大・医進クラス入試」「特進クラス入試」を行っていますが、そこに入ればぜったいに東大や医学部を目標に、というわけではありません。というのも中高の6年間でいろいろな経験をするうちに、個々の目標は流動的に変化します。高校最後の2年間は目標別にきっちりクラス分けをしていますが、それまでに何度も自分の進路ややりたいことを考え、選択できる機会を設けています。
創立100周年記念事業について教えてください。
2028年の創立100周年に向けて、「新しいもの」をいくつか導入します。まず2025年度からは、制服を一新します。ユナイテッドアローズとタイアップしたシンプルかつスタイリッシュなデザインで、家庭での洗濯も可能です。夏服、冬服という概念をなくし、天気や気温、気候に合わせて着用できることも大きな魅力ですし、組み合わせによってさまざまなバリエーションが楽しめます。


食堂も大きくリニューアルします。カフェテリアのように生まれ変わり、ラーニングコモンズ的スペースも作ります。
また現在、中学生は基本的にお弁当を持ってきてもらっていますが、2025年の2学期からは、スクールランチの提供が可能になります。共働き家庭が増えているなか、お弁当作りはご家庭への負担も大きいことも現状です。学校でランチを提供してもらえたらというニーズも増していましたので、その声に応え、食堂のリニューアル前からスクールランチの提供を前倒しで行います。
今後も100周年記念事業については、詳細が決まり次第発表していきますので、ぜひご期待いただきたいと思います。


教えて!学校のこと 試験のこと
M.I君(中学2年生) 特進クラス サッカー部に所属
Q1 中学受験の勉強は、いつ頃から始めましたか。
小5の冬くらいからです。適性検査型入試対策としては、社会と理科を重点的に学びました。Ⅰの作文は、通っていた塾の先生に何度も添削してもらいました。もともと読書が好きだったので、設問を読むスピードは身についていたと思います。
Q2 学校の魅力を教えてください。
設備が整っていることと、先生がたくさんいて、何でも気軽に質問できることです。
Q3 好きな授業は何ですか。
小学生のときから英語を習っていたこともあり、英語は好きですし、得意科目です。また小学生のときは、社会があまり好きではなかったのですが、八王子学園の社会の授業はとてもわかりやすくて楽しいので、地理と歴史が大好きになりました。
Q4 八王子学園でのおすすめの過ごし方を教えてください。
文武両道の学校なので、部活にはぜひ入って欲しいです。僕はサッカー部に入っていますが、先輩との仲もよく、とても楽しいです。
Q5 これからの目標を教えてください。
3つ上の兄が、八王子学園の高校に通っています。兄は成績も良いので、兄に負けないように僕も勉強をしっかり頑張りたいです。中1からそこそこ上位をキープできていますが、気を抜くことなく、この先も常に上位にいられるようにすることが目標です。
H.Tさん(中学1年生) 東大・医進クラス 陸上部に所属
Q1 受験勉強はいつ頃から始めましたか。
公立の中高一貫校の受験を意識し始めたのが小学校5年の夏ごろからです。5年のうちは、通信教育を活用し、6年になってから塾に通い本格的に受験勉強を始めました。
Q2 何に力を入れて勉強しましたか。
公立中高一貫校の過去問を何度も解きました。もう少しやっておけばよかったかな、と思うのは記述対策。作文はどちらかというと得意だったので、あまりやらなかったんです。記述や作文の力は、入学してからも活かされるので、やっておいて損になりません。
Q3 東大・医進クラスを選んだ理由を教えてください。
家の近所に、八王子学園の東大・医進クラスに通っている知り合いが2人いるので、おすすめポイントなどを聞きました。私は中学に入ったら英語を頑張りたいと思っていたので、リーディングの授業を受けられる東大コースを選びました。
Q4 今、とても興味深く学んでいることは何ですか。
探究ゼミで、八王子について調べることがとても楽しいです。八王子に毎日通っているのに、いざいろいろ調べてみると知らないことがたくさんあって、目から鱗の連続。私はお城が好きなのですが、八王子には「日本100名城」のうち、2つがあることを知りました。
- 取材Memo
-
取材に伺ったのは、期末テストの答案返却日。職員室の前には、たくさんの生徒の姿が見られ、先生方から指導を受けていました。自習スペースも多く、波平先生がおっしゃっていた通り、伸び伸びと自分のペースで学べる環境が整っていました勉強に限らず、生徒の自主性を尊重する校風で、その代表的なものが学園祭なのだそうです。高校では、人が乗れるミニジェットコースターも生徒たちが手づくりするとのことで、写真を見せていただきました。金属パイプで骨組みを作り、椅子を固定し、ローラーもついた本格的なもので、完成度の高さに驚きました。当日は教室にコースを作って、来場者を迎えます。こうした生の情報は、学校のInstagramで発信されているので、ぜひチェックしてみてください。