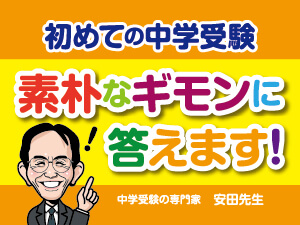相模女子大学中学部の入試は、教科型、適性検査型、プログラミングの3タイプ。「タイプを複数設けているのは、それぞれに自分の長所を活かして受験して欲しいから」とのことです。前回の適性検査型入試に引き続き、今回も適性検査型入試について、入試広報担当の副校長 中間先生に伺いました。

適性検査型入試の特徴は?
「適性検査型入試は、教科の隔てなく、すべての教科に関わる内容が出題される入試問題です。そのなかで、文章を正しく理解する力や自分の考えを表現する国語的な能力と、算数的な見方や考え方と計算の基礎的技術を問います。さらに図や表や文章など、複数の情報を読み取る論理的な思考力を問うことも、本校の適性検査型入試の特徴です。一方で、年号や人物の名前などを知っていなければ解けないような問題はできるだけ出しません。なぜなら、知識量で差がつかないようにしたいからです。解答に必要な材料は問題の中に盛り込んでいますので、極論を言えば、答えはすべて問題の中にある。つまり、問題をきちんと読み取る力があれば答えられる試験で、普段から新聞など、さまざまな文章を読んでいれば、自然と身につく能力だと思います。なお、本校の適性検査型は、1,2,3と分かれていません。適性検査型としてひとつだけ、全体で100点満点、45分間の入試となっています」。
適性検査型入試で見ているのは、いわゆる地頭。知識量で差がつかないようにしているのは、受験勉強の開始が遅れた受験生が不利にならないようにするためで、受験生への細かい配慮が感じられます。作問も、県立の一貫校に寄せるのではなく、相模女子がどのような生徒を欲しいか、といったスタンスで作問していることも大きな特徴です。
出題傾向と採点方法について
「特別な傾向はありませんが、受験生にとっても身近な話題を選ぶようにしています。例えばオリンピックなど、その年に話題になった出来事を取り入れています。作問にあたっては、できるだけ全教科の教員が多く加わり、体育や音楽、家庭科の教員も作問に関わります。採点においては、考える過程をとても重視しています。適性検査型入試の場合、例えば算数では、問1の計算の答えを使って問2を解いて、問2の答えを使って問3を…という問題がよく出題されます。こうした設問ですと、問1の計算を間違えてしまうと、後半の答えも間違いになってしまいます。しかし本校では、仮に問1が間違っていても、問2以降の計算のプロセスや思考回路が正しければ個別に評価しています。そのため採点は非常に大変ですが、時間をかけてていねいに採点しています」。
非認知能力を養う教育
「2019年以来、非認知能力の育成を重点目標に掲げています。その一環として、授業では『考える癖』を養うことを大切にしています。考える『習慣』ではなく『癖』というところがポイントです。というのも『習慣』は意識して行うものですが、『癖』は自然とやってしまうもの。『考える癖』を養うために、授業では各教員が『考える機会を奪わない』工夫を凝らしています。例えば、『わかりません。どうしたらいいですか?』と生徒に助けを求められても、『教えないから自分で考えて』と対応します。自分で間違いを見つけて答えに辿り着く作業の方が、教わった正解より大切だからです。このコンセプトを全教員が共有しているので、どの教科にも生徒たちの非認知能力を育む仕掛けが散りばめられています」。

適性検査型入試を経て入学した生徒さんの特長は?
「ちょっと雑な表現ですが、どっしり感があるというか、肝が据わっている生徒が多いように感じます。入学後の成績は個人差がありますが、いわゆる成績でははかれない部分の力(非認知能力)を持っていることは間違いありません。すごく伸びしろを感じますし、学びを実践につなげられる能力に長けているので、この先いい意味でどう化けてくれるかが楽しみですね」。
受験生へのメッセージ
「非認知能力を育むには、時間がかかります。個人差もあり、その子の能力がいつ伸びるか分かりません。また、無理強いしては本当の力にならないとの考えから、強く引き上げるようなこともしません。本校の教員は、ひたすら粘り強くアプローチを続け、一人ひとりの成長に『伴走』します。その姿勢が本校の特長であり、魅力でありたいですね。受験校選びは、6年間の過ごし方選びです。今の選択が6年間、そしてその先の人生にも影響するのです」。

「適性検査型入試=公立一貫校の入試 というイメージから、公立一貫校を第一志望にすると、そこだけをターゲットにしがちですが、私学でも適性検査型入試を行っている学校は増えていますし、私学はそれぞれ特徴があります。いろいろな学校の説明会に参加してみると、学校によるカラーの違いや、今、そしてこれからの教育や変化する大学受験について知ることもできます。情報をバージョンアップすることは、中学受験においてとても大切なこと。皆さんが、自分にとってよい学校に巡り合い、よいマッチングになることを願っています」。
教えて!学校のこと 試験のこと

Q1.中学受験しようと思ったきっかけを教えてください。
母の勧めから、小4のとき相模原中等教育の文化祭に行きました。この学校に行きたいな、と思い、中学受験することを決めました。
Q2.どんな勉強をしましたか。
塾に入って、適性検査型入試のための勉強を始めました。でも思うように成績が伸びず、小5のとき、一度受験を諦めかけました。受験用の勉強はやめて、塾のオンライン授業で学校の復習をする勉強に切り替えたところ、勉強にも自信ができてきたので、あと一年頑張ってみようと思い、改めて6年から適性検査型入試への勉強を始めました。
4科の勉強のほか、記述対策として、作文を書きました。課題について自分の意見を150字程度で書き、塾の先生に添削してもらいました。
Q3.相模女子を知ったきっかけは?
小6の夏の模試の会場が相模女子で、初めて行きました。正門から入ったときの景色がとてもきれいで、いい環境の学校だなあ、と思ったことをよく覚えています。その後、相模女子の適性検査型入試の体験会に参加してみました。けっこう難しくて、解けない問題もあったのですが、体験会の直後ぐらいから、なぜか模試の成績も上がっていったんです。
Q4.受験本番当日はいかがでしたか。
すごく緊張しました。試験もあまりできなかった気がして自信はなかったのですが、合格をもらって安心しました。合格が自信になり、3日の相模原中等を受けるときは気持ちに余裕を持って全力投球できました。
Q5.相模女子に入学しようと思ったのはなぜですか。
相模原中等が残念な結果になったので、地元の公立に行こうかと迷ったのですが、女子校への憧れもありましたし、思い切って中学からは環境を変えてみようと思い、相模女子を選びました。
Q6.入学後はすぐに慣れましたか。
最初はクラスメイトにも話しかけることができなかったのですが、小学部からの子たちがとてもフレンドリーに話しかけてくれて、入学から1カ月くらいたったころには、友人もたくさんできました。
Q7.適性検査型入試の勉強をしてきたことは、学校生活に役立っていますか。
教科型試験で入学した人に比べると、知識が不足しているかな、と不安もありましたが、まったくそんなことはなかったです。適性検査型の勉強でも、4科目まんべんなく勉強していたことが役立っていると思います。授業もとてもわかりやすいです。
Q8.自分で考える力は身に付いてきましたか。
質問に行っても、先生は答えを教えず、ヒントだけくださいます。そこから友人と話し合ったり、自分で考えたりする癖が身に付きました。答えを導き出す過程の大切さが理解できるようになりました。

Q1.中学受験を考えたきっかけを教えてください。
私は幼稚部から相模女子に通っていました。男女共学の小学部は、男子のほぼ全員が中学受験しますし、女子も受験する子が多いんです。6年になるまで受験を迷っていましたが、受験勉強は無駄にはならないと思い、受験することを決めました。塾に行き始めましたが、スタートが遅かったので、最初は全然ついていけなくて大変でした。
Q2.どんな勉強をしましたか。
教科全般を学びながら、ニュースを見て、感想を150字でまとめる宿題をやりました。第一志望は3日の相模原中等でしたが、相模女子も受けようと思い、入試体験会に参加しました。県立の問題よりは解きやすいなと思ったのですが、解けない問題もありました。でも先生が詳しく解説してくれたのでわかるようになりました。入試体験会はぜったいに参加したほうがよいと思います。
Q3.結果的に相模女子に入学することになったのですね。
3日の県立が不合格だったので、合格していた相模女子に入学しました。もともと通っていた学校だったので、安心感はありました。
Q4.適性検査型入試の勉強は、役に立っていますか。
受験せずにそのまま中学に上がることもできたのですが、受験勉強してよかったと思っています。たとえば私は数学が苦手なんですが、問題を解くときに、数学の設問を国語風に置き換えてストーリーを作って考えると、設問の意図がよくわかるんです。適性検査型入試の勉強で、国語力や思考力、読解力を鍛えたことがとても活かされていると思います。
Q5.相模女子の「ここがおすすめ!」を教えてください。
自然豊かな環境で伸び伸びと学校生活を送ることができます。幼稚園から大学までがひとつのキャンパス内にあるので、コラボ授業などもあって楽しいです。小学部にいるヤギの「バニラ」や、キャンパス内をお散歩している幼稚部の子どもたちを見ると、とても癒されます。

- 取材Memo
-
本当に癒される空間に満ち溢れた学校
生徒さんたちの言葉通り、いつ訪れても自然がいっぱいで、本当に癒される空間に満ち溢れた学校です。プログラミング教育をはじめ、赤ちゃん・子どもたちと触れ合いながら、さまざまな「命」と出会い、人の存在の尊さを体感する機会もたくさんあります。中高時代の6年間は、その先の大学に入学するために学びを深めることも大切ですが、それ以上に、考える力や豊かな感性を身に付けることも大切。相模女子を訪れるたびに、偏差値で学校を選ぶのではなく、環境や教育方針、カリキュラムをきちんと知り、受験生本人が「行きたい」と思える学校を選ぶことの大切さを感じます。