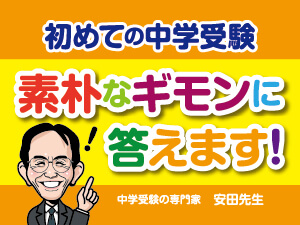聖徳太子の「和」の教えを尊重し、1927年に創立された聖徳学園。
グローバル、STEAM、探究、SDGsなどの教育にいち早く着手し、常に「新しい価値を創造すること」を目標に、世の中の動きを先取りした教育を反映・実践。「一人ひとりの個性や才能を見出し、多方面からサポートしながら伸ばす教育」が注目されています。STEAM教育の業績が認められ、「Apple Distinguished School」に認定されていることからも、同校の教育力の高さがうかがえます。
入試もフレキシブルで、教科型入試(国語・算数の2科、もしくは国語・算数・英語から2科目を選択)に加え、プライマリー入試、特別奨学生入試、プログラミング入試、帰国生入試、そして「適性検査型入試」があり、子どもたちの得意や意欲を活かせるスタイルでの受験が可能です。
今回は、同校の展望などについて、本年度より校長に就任した峯岸渉校長先生に。同校の「適性検査型入試」について、竹内一樹教頭先生に。さらに「適性検査型入試」を経て入学した生徒さん3名にお話を伺いました。
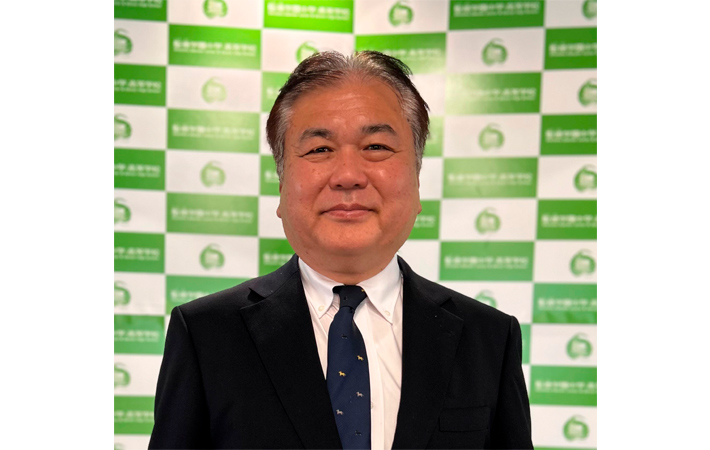
本年度から校長に就任されましたが、これからの聖徳学園の展望について教えてください。
「本校はこれまでも、“まずはやってみよう”を合言葉に、新しい取り組みを行ってきました。生徒と先生の間にまったく壁がなく、何でもオープンに話せる関係を活用して、これまで以上に生徒と先生が一緒になって、どんどんおもしろいこと、やりたいことにチャレンジしていきたいと思っています。
生徒たちの取り組みは、私はもちろんすべての教員たちで共有しています。面倒見がよく、生徒と関わることが大好きな先生ばかり。一方的に勉強だけ教えればいい、というスタンスの先生は、本校にはいないと言っても過言ではありません」。
どんな校長先生でありたいですか。
「私は元体育の教員で、昨年まで授業を担当していました。今は校長という立場ですが、生徒にしてみれば、まだ“体育の先生”というイメージが強いかもしれません。校長になっても、できる限り生徒と接し、生徒の近くにいたいと思っています。校内で会ったときに立ち話をしたり、ハイタッチをするのも、これまでと変わりません。
学校運営に関しては、どんな学校にしたいか、というよりも、どんな人になってほしいか、という部分を大切にしたいと思っています。今、社会はどんどん変わっていて、未来が見えない状況です。だからこそ、一人ひとりが自分で道を切り開き、挑戦して答えを導いていける『人』を育てたいのです。
学校内で先生だけから教わるのではなく、生徒から発信される“やりたい”を軸にどんどん外に飛び出して、いろいろな人とかかわりを持ちながら成長できる機会を増やしたいですし、そのサポートに力を注ぎたいと思っています」。


聖徳学園の「適性検査型入試」の特徴を教えてください。
「本校の適性検査型入試は、2科型・共通2科型・3科型の3つの中から選択できます。2科型は都立三鷹中等教育学校(以下、都立三鷹)、3科型は都立武蔵高等学校附属中学校(以下、都立武蔵)の問題を参考に作問しています。都立立川国際中等教育学校(以下、立川国際)・都立南多摩中等教育学校(以下、都立南多摩)の受検生におすすめです。問題も採点基準も公立一貫校と非常に近いものとなっています」
どのような受験生が多いのでしょうか。
「都立三鷹を第一志望とする受験生が多いですね。あとは、都立武蔵、立川国際、都立南多摩、都立大泉(東京都立大泉高等学校・附属中学校)でしょうか。
試験は、公立一貫校と同様の集合時間・検査時間に設定して2月1日に実施しており、翌2日の合否を知ったうえで、公立一貫校の適性検査に臨むことができます。そのため公立一貫校の対策として受験する方も多くおります」。
適性検査型入試を経て入学する生徒さんには、どのようなことを期待していますか。
「適性検査型入試は、内容もとても高度で、受験生は大人も解けないような問題にずっと取り組んできたわけです。受験勉強を通じて、多角的に物事を見て、答えを導き出す力も身に付いています。本校の、様々なことに自らチャレンジできる環境は、適性検査型入試で入学した生徒に適合しているのではないでしょうか。多くの活躍の場を期待しています。2025年春、塾に通うことなく東大に現役合格した生徒は、適性検査型入試で本校に入学しました」。
受験生にメッセージをお願いします。
「本校や私学の魅力を理解してくださる方が増えてきていると実感しています。2月1日の入試で初来校した受験生が、合格の後に本校を選んでくれるのはとても嬉しい事ですね。
26年度入試も従来型通りの複数入試を行います。大切なのは、どの入試で入学しても、『この学校でよかった!』と生徒自身が感じてくれること。『活き活きと学校生活を楽しみ、自分の得意を伸ばしている生徒が多い』ことは、本校の伝統でもあります。
学校生活や生徒たちの頑張る姿は、ホームページや動画でも発信していますので、ぜひご覧になっていただければと思います」。
教えて!学校のこと 試験のこと

Q1. いつ頃から「中学受験」をしようと思いましたか。きっかけも教えてください。
小5くらいのときから、都立の一貫校に行きたいと思い、塾に通い始めました。立川国際を第一志望に、勉強していました。
Q2.「聖徳学園」の適性検査型入試を受けようと思ったのはなぜですか。
都立に向けて受験勉強をしていたときは、志望校としては考えていませんでしたが、直前になって、受けてみようと思いました。3つ年上の兄が聖徳学園中・高に通っていたので、文化祭や体育祭は見に来たことがあり、身近に感じていた学校だったからです。
Q3. 入学してみていかがですか。
都立は残念な結果になりましたが、気持ちを切り替えて聖徳学園で頑張ろうと思い、入学を決めました。兄が通っていたことも安心感につながりました。想像していた以上に先生と生徒の距離が近く、やりたいことに挑戦できるし、結果的に聖徳に入ってよかったと思っています。
Q4. 適性検査型入試で入学した生徒の特長を教えてください。
科目型で入学した子のほうが、いわゆる受験勉強的なことをしているので、最初はついていけるかな、と不安でした。でも、数学と英語でテスト点数によるクラス分けをしたら、私も含め、適正型の子が上位クラスに入っているんです。適正型の勉強で身に付いた読解力、考える力などは、とても役に立つんだなあ、と実感しています。
Q5. 今、どんなことに力を入れていますか。
中3のときから、「地域貢献プロジェクト」に参加しています。私はこの取り組みの中で、聖徳学園の中1生がスプリングキャンプで訪問する新潟県の阿賀町の方々と一緒にプロジェクトを行っています。現在は高1の有志8人ぐらいで行っていて、この春休みには阿賀町を訪れて、地元の方々と交流しながら地方創生のためにできることを考えました。今は阿賀町観光協会の方と一緒にSNSで阿賀町の情報を発信しています。
もともと地方創生に興味がある先輩の発案からスタートしたプロジェクトなのですが、情報科の先生が大学時代に地方創生活動に携わっていたことを知り、先生にもアドバイスをもらいながら取り組んでいます。本校には、いろいろな専門分野を持つ先生が多いので、やりたいことがあれば、先生に相談して一緒にできるのが、とてもすばらしいと思います。

Q1. いつ頃から「中学受験」をしようと思いましたか。きっかけも教えてください。
5年生の4月頃です。いとこが中学受検して、都立中高一貫校に通っていて勧められたことがきっかけです。私は都立三鷹を第一志望に設定し、塾に通い始めました。
Q2.「聖徳学園」の適性検査型入試を受けようと思ったのはなぜですか。
塾の先生のすすめです。「都立三鷹を受けるのなら、聖徳学園も受けておいたら?」と6年生の12月ぐらいにすすめられ、受験することにしました。
Q3.「対策」として、どのような勉強をしましたか。
6年生になってからは、都立三鷹の過去問をひたすら解きました。
もともと読書や文章を書くことが好きだったので、国語はあまり苦労しませんでしたが、算数系は苦手でした。都立三鷹は算数にからむ問題が多いので、そこは苦労しました。
塾で先生に質問し、理解できるまで頑張って勉強しました。
Q4.「聖徳学園」の入試を受けてみていかがでしたか。
聖徳学園の説明会には参加していなかったので、入試当日の2月1日に初めて学校に向かいました。試験日の生徒さんたちのサポートと気配りを体験し、「とても雰囲気がいい学校だなあ」と思いました。
適性検査入試の内容は、都立三鷹の過去問によく似ていて、都立三鷹の問題を解いているような感覚でした。
Q5. 入学してみていかがですか。
第1志望の都立三鷹は、残念な結果になり地元の公立にするかどうかで迷いましたが、入試の日に感じた聖徳学園の雰囲気の良さを思い出し入学を決めました。グループワークも多く、皆で話し合いながら進める授業がとても楽しいです。いろいろな入試で入学してくる生徒の個性がうまくミックスされている学校です。
Q6.「聖徳学園でよかった」と思えるのはどんな点ですか。
STEAMの授業では、SDGsを題材に5分ほどのショートフィルムを作成しています。完成した作品は、「SDGs映画祭」で発表して映画監督の方に見ていただくのです。「中1から挑戦させてもらえる環境ってすごい」と思います。
また、委員会活動などは、もし地元の公立に行っていたら、「次は別の人に」と見送られてしまいそうですけど、聖徳学園は自分がチャレンジしたい事は何回でも挑戦できますし、先生方も積極的に背中を押してくださいます。

Q1.「中学受験」をしようと思ったきっかけを教えてください。
小学生の頃、医療系テレビドラマを見たことがきっかけで医師に憧れをいだきました。「医学部に進むためには、レベルの高い環境で学ばなければ」とも思い、都立大泉高等学校附属中学校(以下、都立大泉)を目標に勉強を始めました。
当初は個別指導塾に通塾していましたが、小5の冬に、公立中高一貫校への合格実績が高い塾に移りました。
Q2.「聖徳学園」を受験した理由を教えてください。
「私立だけど適性検査型入試を実施している学校があるから、公立中高一貫校の入試前に、試験の雰囲気に慣れるためにも受験してみては」と、塾の先生に勧められたからです。
Q3. 聖徳学園」に入学することになったいきさつを教えてください。
本命の都立大泉に自信を持って受検したのですが、失敗してしまいました。
都立大泉がダメなら地元の公立に行こうとも思いましたが、僕があまりにもショックを受けているので、両親が合格していた聖徳学園のことをいろいろ調べて教えてくれました。
自分自身でも聖徳学園のことを調べてみると、入りたかった書道部があったこと、高校の選抜クラスの偏差値が60ほどありレベルが高いことを知りました。「だったら、ここでもいいかな」と。
Q4. 入学してみていかがでしたか。
念願だった書道部に入りました。もともと書道を習っていたのですが、聖徳学園の書道部の顧問の先生から、これまでとはまったく異なる「書道の世界」を教わり、とにかく部活が楽しくなりました。顧問の先生との出会いが「人生のターニングポイントになった」と言っても過言ではないくらいです。
Q5. 書道部ではどんな活動をしていますか。
大会に出場する機会がたくさんあります。尊敬できる先輩もいて、刺激になりました。
僕自身は、中1の夏の全国大会で「ベスト30」に選ばれ、中3時には、お正月に明治神宮の回廊に掲示される作品に選出されました。こうした成功体験が、自信になりました。自信があるときに字を書くと、すごくいい線が出るのです。
都立大泉は高校生に進級してからでないと書道部への入部ができないので、仮に都立大泉に合格していても・・。中学時代からこんな素晴らしい体験はできなかったと思います。
Q6. 学校の勉強はいかがですか。
書道に情熱を注いでいたので、中学時代に猛勉強した記憶はないのですが、成績は常に上位をキープしていました。「授業を真面目に受けていたこと」「適性検査型入試で身に付けた基礎学力や読解力があったこと」がその理由かもしれません。
授業はとてもわかりやすかったです。
Q7. この先どのような進路を考えていますか。
「聖徳学園」で書道の魅力を発見したこと、尊敬する恩師に出会ったことで、将来は「書」に携わりたいと大きな目標が見つかりました。作品を書くだけでなく、そのパフォーマンスも披露しながら、「書道の魅力を世界に発信」していきたいと思っています。
大学は、書道をはじめ、芸術、学問を幅広く学べる「国立大学」を第一志望に頑張っています。そのために、高2からは「難関国公立・理系クラス」に入りました。芸術系の大学を選ばなかったのは、これから先に芸術系で生きていくにしても、将来は幅広い知識が必要だと思ったからです。
Q8.「聖徳学園」でよかった!と思っていることを教えてください。
先生と生徒の距離が近く、本心で向き合うことができます。書道はもちろん、美術系、音楽系にも長けた先生方がいるので、学校外で学ばなくても、先生方にどんどん教わることができます。
芸術系に限らず、やりたいことを探し続けていれば、何かに巡り合うことができる学校ですし、それに出会える機会がたくさんあります。
Q9.「適性検査型入試」のアドバイスをお願いします。
一番大切なのは国語力だと思います。国語力、つまり読解力がないと、その他の教科の問題も解けません。適性検査型入試の勉強で身に付けた読解力や思考力は、基礎学力の「貯金」になって、中学入学以降も必ず役に立ちます。
- 取材Memo
-
互いに協働しながら認め合い、個を伸ばす教育
いろいろなスタイルの入試を経て入学してくる生徒たちをミックスし、グループワークを多く取り入れることで、「互いに協働しながら認め合い、個を伸ばす教育」を体現。生徒たちは自然に「自分の居場所や好きなこと」を見つけています。
生徒の活躍ぶりがよくわかる学校紹介動画は、「動画研究部の生徒たち」が作成したものも多く、そのクオリティの高さに驚きます。「好きなこと」に徹底的に打ち込める学校だからこそ、さまざまな分野において中高生とは思えないほどの高いスキルが身に付くのではないでしょうか。
受験日には、書道部の生徒たちが書いたメッセージが出迎えてくれるとのこと。知れば知るほど奥深く、可能性に満ちた「聖徳学園の魅力」を、ぜひ学校に足を運んで見つけてください。公立中高一貫校の併願として考える場合も、事前に説明会に参加することをお勧めします。